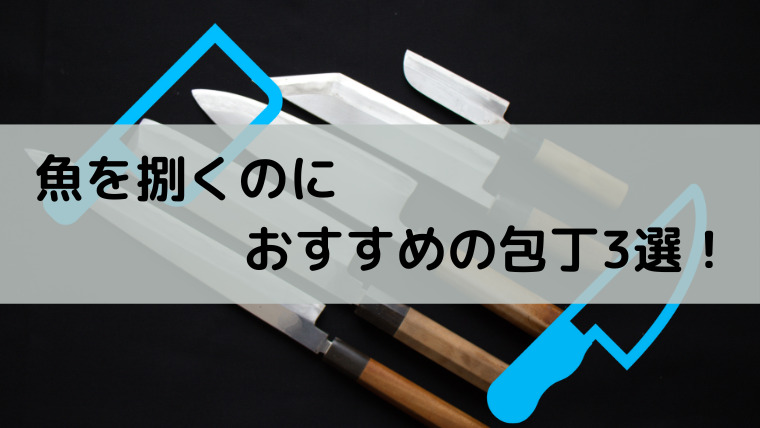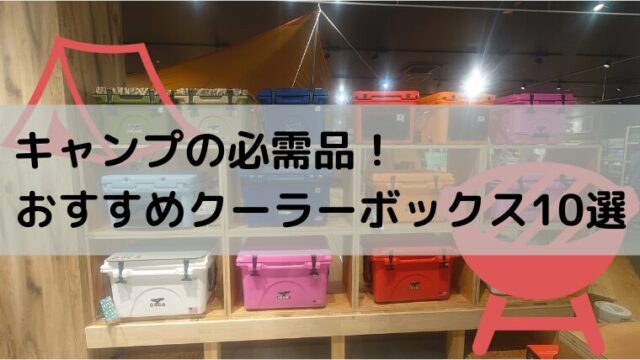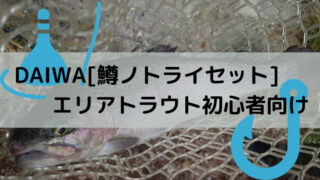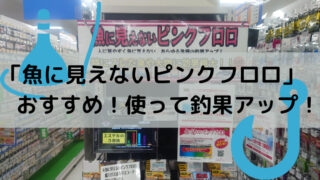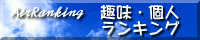釣りをしていて自分で魚を捌きたいと思った方はいないでしょうか。
私も実際、釣った魚を捌きたいなとか考えたりはします。
今回は釣りから派生して
釣った魚を捌くために必要な包丁のおすすめを紹介します。
これを見ればどんな包丁を買えばいいかわかるはず。
特に合羽橋(東京)や堺(大阪)などにある
包丁専門店に行くのが難しい人は読んでみてください。
私が良くいく居酒屋の店主は寿司屋などで修業をした方で、刺身を捌く姿ははやりカッコいいと感じますね。
目次
魚を捌く包丁の種類
では早速おすすめ商品を紹介と行きたいところですが、
前提になる包丁の種類は伝えておきたいと思います。
もう知っているという人はこの部分は読み飛ばして頂いてOKです。
ここで紹介している包丁の種類は有名どころだけを記載しています。
記載してないものには「骨切」「鰻裂き」「蛸引き」「フグ引き」なんかは個々では紹介しませんのであしからず。
出刃包丁
出刃包丁は魚を捌く際に、太くて硬い骨を切るなどの重要な役割を果たしてくれます。
また、刃先が鋭いことから、粘りのある魚の身に刃がくっつきにくく、魚を3枚おろしにする際にも使いやすい包丁です。

力を入れて切る場面も多く、切れ味だけでなく丈夫さや握りやすさも求められます。
柳刃包丁
刺身にする時に魚介類を切るのに適した包丁ですね。
刃が薄く、切れ味が良いのが特徴です。

三徳包丁(万能包丁)
日本の家庭で最も一般的な包丁で魚・肉・野菜など、さまざまな食材を切ることができる万能包丁として人気があります。

ほとんどの家庭は置いてる包丁は三徳包丁だけなんて、まぁ普通といえば普通ですね。
さきほど上げた「出刃」「柳刃」「蛸引き」なんてまずまず使う機会はありませんし。
魚を捌くのにおススメの包丁
貝印 関孫六 銀寿 本鋼
まずは日本が誇る刃物メーカー[貝印]の包丁
「関孫六」シリーズの中でも特に人気の高いモデル
『関孫六 銀寿 本鋼』
このモデルは出刃、刺身、三徳と様々あるうえ
サイズ(刃渡り)も複数取り揃えているので欲しいと思う1本を買うのにはちょうどいいですね。
「銀寿 本鋼」の最大の魅力は切れ味と耐久性になり、
本鋼を使用していることで切れ味が長持ちし、研ぎやすいのが特徴です。
しかも高級刃物材である本鋼を使用しているにもかかわらず、
比較的リーズナブルな価格で購入することができるので
初めて本格的な包丁を購入する方におすすめ!!
刺身が食べたいと自身で捌く人は長く愛用している様ですね。
刺し身が食いてぇ。刺し身が。
と言うわけで、
関孫六 銀寿 本鋼。
シャプトン刃の黒幕んの8000番と12000番を購入。いやー。
youtubeでお勉強1時間、研ぎ3時間って、鬼みたいに時間かかったわ。。。 pic.twitter.com/yHf8YNKxdI— 独活大木 (@oumiyan) February 20, 2022
堺一文字吉國
六百年の伝統を持つ堺打刃物であるブランド「堺源吉」の中でも
名高いハイエンドの『堺一文字吉國』もおすすめですね。
この『堺一文字吉國』も出刃、刺身、三徳と様々あるうえに、
サイズ(刃渡り)も複数取り揃えているので欲しいと思う1本を買うのにはちょうどいいですね。
プロの料理人も使っているブランドなので、相応の値段がします。
しかしその分、切れ味、握り、使い心地はいいです。
またしっかりと手入れをしてあげれば長く使えるので愛着もわきますね。
一応「堺源吉」の中でも『堺一文字吉國』とは
別に入門向けにリーズナブルな価格帯の包丁もあるので
『堺一文字吉國』はまだ自分にはって方はこちらを選んでもいいかもしれませんね。
本霞・玉白鋼
正本といえば築地卸売市場(今は豊洲卸売市場に移転してますが)で有名な刃物ブランド
その正本の包丁でもハイエンドモデルなのが『本霞・玉白鋼』
正直に言ってこのクラスになると3~4万円は余裕でしますし、
「蛸引包丁」や「薄刃包丁」なんかになれば10万えん以上なんて当たり前の部類です。
それでもプロの使っている包丁を自分も使いたいと思ったら候補に入れてみてはいかがでしょうか。
マグロ解体用の包丁を作っているぐらいには、プロの包丁を作っているブランドですね。
銃刀法で捕まる包丁、衝動買いしちゃいました😀
🔪正本総本店
本霞玉白鋼マグロ切庖刀(鮪包丁)
刃長600mm
白紙二号鋼(白二鋼)、極軟鋼(地金)
定価326000円#サヤ付きだと刀に分類される#マグロ包丁#正本#刃渡り60cm#ちなみに銃刀法は免許あり pic.twitter.com/3QJ6JMYsty— 🐟しぶちこ🍣 (@sibutiko) January 4, 2023
適度な刃渡り
また事前知識として魚を捌くための包丁は、
捌く魚の大きさなどによって適度な刃渡りの長さを選ぶ必要があります。
出刃包丁
アジなどの小さな魚であれば刃渡り13cm前後のサイズを選んでください。
50cmを超えるような中型から大型の魚を捌く場合には刃渡り16cm前後は欲しいですね。
また刃渡りが長すぎると、出刃包丁は重くなり扱いにくいので
自分が扱いやすいと思うサイズをを選ぶようにしましょう。
柳刃包丁
刺身を切る際は包丁を手前に引いて一回で切ると身が崩れず美味しく切れることから、
刺身包丁は一度で引いて切る事が求められるます。
そのため出刃包丁などと比べると刃渡りが長いのが特徴ですね。
料亭やお寿司屋などの飲食店では刃渡り30cmなどの長い刺身包丁を使用するかと思いますが、
長すぎると一般家庭のキッチンでは扱いにくいので、刃渡り21cmから24cm程度が扱いやすいかと思います。
三徳包丁(万能包丁)
これは自身の自宅でキッチンにある包丁を見てもらえばぶっちゃけそのサイズは目安と思っていいですね。
まぁ大体が刃渡り17cm前後がおすすめです。
短すぎず長すぎず、キッチンで扱いやすい長さであることに加え、肉や野菜など様々な食材に適した長さです。
刃渡りのほかに購入時にチェックする点
素材
素材は大きく、「鋼」と「ステンレス」があり、それぞれのメリット・デメリットがありますね。
鋼
鋼は硬い素材のため、切れ味が鋭いことが一番のメリットです。
デメリットは鋼は錆びやすく切れ味が落ちやすいため、こまめに水気を取ったり乾かしたりする手入れが必要です。
また砥石を使って定期的に包丁を研ぐ必要もあります。
ステンレス
ステンレスのメリットは何といっても錆びにくい!!
そのためこまめに水気を取ったり乾かしたり研いだりする必要が無いのが良い点ですね。
逆に言えばステンレスは鋼に比べて柔らかい素材なので、安価な包丁だと切れ味が悪いケースがあります。
柄の素材
木製
木製の柄は使うほどに手に馴染んできて使用感(味)が出てくるのが特徴です。
水気などによる劣化があるので、メーカーのアフターサービスで長く使い続けるのがおすすめです。
ステンレス
ステンレス製の柄の特徴は刃と柄が一体になっていることが多く、継ぎ目がないこと。
隙間に水が浸入することがないので劣化が少なく、長く使用することができます。
基本的には握りやすいような設計になっている包丁が多いです。
柄の握り
小判型
柄の断面が楕円になっており力を入れやすいことが特長
魚を捌く際に硬い骨を切る出刃包丁に向いている形です。
栗型
柄の断面の一か所が尖っていて栗に似た形をしており、
この突起に指を引っ掛けることで作業がしやすくなり、刺身包丁は主に栗型です。
八角型
柄の断面が八角形になっており手にフィットしやすいことが特徴
高級な包丁に採用されていることが多い形ですね。
まとめ
今回は当ブログでは例外的な魚を美味しくさばくための包丁を紹介しました。
魚が好きで自分でも刺身を安く美味しく食べたい人は、スーパーで買わずに自分で鮮魚店にいってまるまる一匹買って捌く人がいます。
ぜひ釣りをする方で魚を食べるのが好きなら、
マイ包丁をGETしてはいかがでしょうか。