本記事は全国共通の法令と地域ルールを横断整理。水産庁・環境省の最新ガイドライン、漁業法や外来生物法、河川法・港湾法、漁協の遊漁券、禁漁区・サイズ制限、海上保安庁の安全基準まで網羅。
結論としては事前確認と遊漁券・ライフジャケットの徹底で合法かつ安全に楽しめ、47都道府県の調べ方と罰則回避の要点も分かります。管理釣り場や遊漁船のルールも解説。トラブルを避けるマナーも把握できます。
日本の釣り規則の全体像と検索意図
「釣り 規則」を調べる多くの人が知りたいのは、どこで・いつ・どの魚を・どの道具で・どれだけ採ってよいのかという実務的な基準と、それを誰が定め、どこで確認できるかという導線です。
本章では、日本の釣りに関わる国・都道府県・漁協・管理者といった複数レイヤーのルールの関係を俯瞰し、検索意図(禁漁期間やサイズ制限、立入可否、遊漁券の要否、外来種の扱い等)を最短で満たせるよう、一次情報へのアクセス方法を明確化します。
| レイヤー | 主な根拠 | 定める主体 | 主な内容 | 確認先の例 |
|---|---|---|---|---|
| 国の法律・指針 | 漁業法、外来生物法、自然公園法 など | 国(省庁) | 採捕の基本原則、特定外来生物の禁止、国立・国定公園内の行為規制 等 | 水産庁、環境省の公式サイト |
| 都道府県の規則 | 内水面・海面漁業調整規則、条例 | 都道府県 | 禁漁区・禁漁期間、漁法制限、サイズ制限(全長)、採捕量の上限 等 | 都道府県の水産課・内水面担当ページ |
| 漁協・管理者のローカルルール | 遊漁規則、遊漁承認(遊漁券)条件 | 漁業協同組合、河川・湖沼の管理者 | 遊漁券の要否・料金、対象魚、エリア区分、リリース義務、エサ・撒き餌の可否 等 | 各漁協の掲示・公式案内、現地看板 |
| 管理釣り場のレギュレーション | 施設利用規約 | 民間・自治体の管理者 | バーブレスフック限定、持ち帰り匹数、キャッチ&リリース可否、ルアー・フライ指定 等 | 管理釣り場の公式サイト・受付 |
基本的な優先順位は、国法 > 都道府県規則 > 漁協・管理者の規則(現場の詳細ルール)という階層で、下位の規則が上位法令より緩くなることは許されません。
実際に釣行する際は「国の禁止=絶対にNG」「都道府県の規則=地域共通の基準」「漁協・管理者の規則=現場運用」と理解し、最終判断は現地の掲示や公式情報で照合します。
釣り規則の定義と対象範囲
本記事で扱う「釣り規則」とは、法律・条例・規則・管理要領・施設レギュレーションなど、釣り(遊漁)に伴う採捕や道具、立入り、持ち帰りに関するルール全般を指します。対象範囲は、海と内水面(川・湖・ため池)にまたがり、漁業権の設定の有無や保護区の有無によって細分化されます。
とくに確認すべき代表的な項目は次のとおりです。
- エリア規制:立入禁止区域、禁漁区、水域の区分(漁港・防波堤・自然海岸・河川区間・ダム湖・管理釣り場)
- 期間規制:禁漁期間、夜間の可否、季節による漁法制限
- 資源保護:サイズ制限(全長)、持ち帰り(日)数量制限、保護対象種の採捕禁止、キャッチ&リリース指定
- 漁具・漁法:針・ハリス・トレブルフックの使用条件、撒き餌の可否、活餌の規制、投光・集魚の扱いなど
- 手続・表示:遊漁券の購入要否、携行義務、現地掲示・標識の遵守
- 外来種対応:特定外来生物の運搬・放流禁止、現場回収の要請方法
同じ魚種でも場所が変わればルールが変わる(内水面=漁協中心、海面=都道府県規則中心+港湾等の管理ルール)ため、対象水域と管轄を最初に特定し、そこから該当する規則を順に当たるのが最短ルートです。
水産庁の遊漁ガイドラインの位置付け
水産庁は、遊漁(レクリエーションとしての釣り)に関する基本的な考え方、資源と漁場環境の保全、漁業者・遊漁者の共存に向けた留意点などを整理し、一次情報や周知資料を提供しています
これらは各現場で義務となる個別規則そのものではありませんが、都道府県の漁業調整規則や各漁協の遊漁規則を読み解く際の“共通言語”として機能する指針であり、資源保護(サイズ・数量・禁漁期間)、漁場秩序(立入・マナー)、安全配慮等の項目が互いに矛盾しないよう運用されることを目指しています。実務では、水産庁の情報で全体像を掴み、該当都道府県と漁協の規則に落とし込む流れが有効です。
環境省の外来生物法と自然公園法の要点
環境保全に関わる横断的な規則も、釣り実務に直接影響します。
第一に外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では、オオクチバス・コクチバス・ブルーギルなどの特定外来生物について、原則として飼養・保管・運搬・放流が禁止されています。釣りの現場では、これらの魚種を別水域へ移動させる行為や再放流(リリース)が規制対象となる場合があるため、地区ごとの案内や回収ボックスの運用を必ず確認します。(参考:環境省「外来生物法(特定外来生物)」)
第二に自然公園法は、国立・国定・都道府県立自然公園の区域や区分(特別保護地区など)ごとに、動植物の採取・工作物の設置・火気利用・立入り等の行為を制限します。公園内水域での釣りは区域・行為の指定に左右されるため、釣行前に「該当区域の区分」と「許可・届出の要否」を確認することが法令遵守の出発点となります。
法律と行政ルールの基礎
漁業法と漁業権の基礎知識
日本の釣り(遊漁)は「自由に楽しめる」イメージがありますが、海・川・湖それぞれで適用される法令や権利関係が明確に存在します。中心となるのが漁業者の権利と資源管理を定める漁業法で、特定区域や資源に対して排他的に採捕できる「漁業権」が設定されています。釣り人はこの漁業権を侵害しない範囲で遊漁を行う必要があります。
特に沿岸の貝類・海藻(アワビ、サザエ、トコブシ、ナマコ、ウニ、テングサなど)は共同漁業権の対象であることが多く、たとえ自家消費目的でも無断採取は違法となり得ます。磯場での素潜り・採集行為は自治体ごとに厳格な規制があるため、釣行前に対象水域の権利設定と規制内容を必ず確認してください。
| 漁業権の種類 | 概要 | 典型的な対象 | 釣り人の留意点 |
|---|---|---|---|
| 共同漁業権 | 漁協などが保有し、一定区域での採捕(主に沿岸の採介藻類)を管理 | アワビ、サザエ、ナマコ、ウニ、海藻(テングサ等)、アサリ など | 権利区域内での採取は不可。釣りの外道としての持ち帰りも違法となる場合がある |
| 区画漁業権 | 区域を区切って養殖・増殖等を行う権利 | カキ・ノリ・ワカメ等の養殖施設、垂下施設 | 養殖施設への接近・係留・釣り糸の投入は危険・損壊の恐れ。区域への立入自体が規制されることもある |
| 定置漁業権 | 定置網など固定式の大型漁具を設置し操業する権利 | 定置網一帯(網口・導網・浮標で区画) | 網の近傍侵入・ラインの引っかけは重大トラブル。標識・ブイの外側を十分に離隔する |
内水面(川・湖)では、漁業法に基づき漁協が「遊漁規則」を定め、遊漁証(いわゆる遊漁券)を発行して資源管理(禁漁期間・サイズ・方法)を実施します。対象魚(アユ、ヤマメ、イワナなど)が放流や保護管理の対象である場合、遊漁券の携帯・掲示が義務付けられるのが通常です。海では一般的な「遊漁免許」はありませんが、漁業権や各種規制に抵触しない範囲に限られる点に注意してください。
都道府県の内水面漁業調整規則と海面漁業調整規則
資源保護と利用調整の実務的なルールは、都道府県が定める「内水面漁業調整規則」「海面漁業調整規則」に詳細化されています。これらは漁業調整委員会等の審議を経て告示され、具体的な禁止区域・禁漁期間・最小体長・使用できる漁具(ハリ数、餌・コマセ、銛・やす・水中銃等の可否)を規定します。自治体により内容・更新時期が異なるため、同じ釣り方でも県境を越えると適法性が変わる点に留意しましょう。
| 区分 | 対象水域 | 主な規制例 | 典型的な手続き | 確認先の例 |
|---|---|---|---|---|
| 内水面漁業調整規則 | 河川・湖沼・ため池等 | 禁漁期間や保護水面、最小体長、餌・撒き餌の禁止、リリース義務、夜間採捕の制限 | 漁協の遊漁券の取得・携帯、釣法・エリアの遵守 | 都道府県水産担当部署、内水面漁協、ダム・湖沼管理者の掲示 |
| 海面漁業調整規則 | 沿岸海域・港湾内の海面 | 特定魚種の採捕禁止・サイズ制限、潜水採捕の可否、コマセや集魚灯の制限、遊泳・航路付近の禁止 | 規則の遵守(一般に免許制ではないが、漁業権・保護区の尊重が必須) | 都道府県水産担当部署、港湾・漁港管理者の掲示、海上保安庁の安全情報 |
「他県で問題なかった方法が、この県では禁止」や「昨年はOKだったが今年は禁漁」というケースは珍しくありません。県の最新告示・現地掲示・漁協の案内を釣行毎に確認し、疑義があれば管轄へ照会するのが安全です。
河川法 港湾法 海岸法と立入禁止区域
釣りの適法性は「魚を採る行為」だけでなく、「場所に入る行為」でも左右されます。水域や施設の管理者は、治水・港湾運営・沿岸保全の観点から立入を制限・禁止する権限を持ち、違反すると退去・指導や罰則の対象になる場合があります。以下は釣り人が直面しやすい管理法令の要点です。
河川法のもとで国土交通省や都道府県が管理する一級・二級河川では、ダム・堰・樋門・取水口・排水樋管・橋梁工事ヤード等が管理区域となり、管理者が安全確保や施設保全のために立入禁止や立入制限を設けることがあります。増水放流やゲート操作は予告なく行われる場合があるため、警報設備・サイレン・掲示に従い、立入禁止ロープやフェンスを越えないことが基本です。
港湾法に基づき港湾管理者(都道府県・政令市など)が所管する岸壁・防波堤・物揚場・航路・泊地では、船舶運航や荷役の安全が最優先されます。貨物船の離着岸区域、作業中の岸壁、危険物荷役区域、航路・防波堤開口部周辺は立入または釣りが禁止・制限されることがあり、係留索やプロペラ洗流、作業クレーンの下などは極めて危険です。漁港でも同様に管理者(漁港漁場整備法に基づく)が立入区分を定め、漁業活動を阻害する行為を禁じています。
海岸法の対象となる海岸保全区域では、防波・防潮堤、離岸堤、胸壁、消波ブロックなどの海岸保全施設が保全・管理されています。工事中や高波時の立入規制、施設の損傷につながる行為(ブロックの上での無理な移動・器具の固定など)の禁止が掲示されることがあり、標識に従う義務があります。
| 施設・区域の例 | 管理法令 | よくある規制 | 釣り人の実務ポイント |
|---|---|---|---|
| ダム・堰・放流設備周辺 | 河川法 | 立入禁止・危険水域指定・ロープ内進入禁止 | サイレン・警報灯・掲示の指示に従い、増水の兆候で即時退避 |
| 港湾の岸壁・防波堤・航路 | 港湾法(港湾管理条例等) | 作業中の立入禁止・航路付近の釣り禁止・係留禁止 | 「関係者以外立入禁止」「立入制限区域」標識を遵守し、船舶優先を徹底 |
| 海岸保全施設(防潮堤・離岸堤等) | 海岸法 | 工事区間の立入禁止・施設損傷行為の禁止 | 工事予告・通行止の告示を事前確認し、仮設通路以外に立ち入らない |
「釣り禁止」と明記がなくても、立入禁止・立入制限・危険区域の表示がある場所では釣り行為も当然に禁止または違法となる場合があります。現地の標識・柵・ロープ・カラーコーン・フラグは法令・条例に基づく管理の現れであり、撤去・移動・無断越境は厳禁です。
海上保安庁の航行安全とライフジャケットの着用
海上保安庁は海難防止・交通の秩序維持・救難の中核機関で、航行警報、危険区域、海象・潮流等に関する情報の発信や、巡視船艇・航空機による安全確保活動を行っています。防波堤の開口部・航路・船道・フェリー桟橋周辺は船舶の通行が優先で、ラインや仕掛けの投入・横断は衝突回避の妨げやスクリューへの巻き込み事故につながりかねません。夜間や視程不良時は特に、船舶・作業船・プレジャーボートの動静に注意し、キャスト方向と回収タイミングを慎重に判断しましょう。
小型船舶(遊漁船・プレジャーボート等)に乗船する場合、法令により乗船者のライフジャケット(救命胴衣)着用が義務付けられ、船長には着用確認の責務があります。基準に適合した製品(いわゆる「桜マーク」の型式承認・適合品)を選び、適正なサイズ・装着方法を徹底してください。岸壁・磯・防波堤など陸上からの釣りでは法的義務がない場合でも、転落・波しぶき・うねり・足場不良のリスクが高い場所では着用が強く推奨されます。
| シーン | 法令上の要点 | 安全の実務ポイント | 相談・通報の目安 |
|---|---|---|---|
| 遊漁船・プレジャーボート | 乗船者のライフジャケット着用義務(船長の遵守義務) | 型式適合品を常時着用。航路・定置網・養殖施設の離隔を徹底 | 緊急時は118番(海上保安庁)。出港前に装備・気象海象を確認 |
| 港湾内・防波堤釣り | 港湾管理者の立入規制・作業区域の制限に従う | 航路・開口部では船舶優先。夜間は視認性確保(ライト・反射材) | 危険行為・漂流物の発見時は港湾管理者や118番へ通報 |
| 磯・サーフ | 立入禁止・保全区域の規制に従う | 救命胴衣・滑り止め装備・離岸流や高波予報の確認 | 急変時は無理をせず退避。事故時は118番へ |
「釣れている場所」よりも「安全に釣れる場所」を優先し、標識・掲示・航行ルール・着用義務の四点を守ることが、法令遵守とトラブル回避の最短ルートです。
フィールド別の釣り規則
フィールド(海・川・湖・管理釣り場)ごとに、所管や適用されるルール、確認先が異なります。したがって出発前の下調べが重要です。現地の掲示・公式発表(自治体・港湾管理者・漁協・施設運営者)が最優先であり、通例よりも掲示内容が優先されます。以下では、場所別に想定される規則と、違反を避けるための確認手順を整理します。
| フィールド | 主な管理主体 | 代表的な規制項目 | 事前確認先 |
|---|---|---|---|
| 海(防波堤・砂浜・磯) | 港湾管理者・自治体・漁港管理事務所・海岸管理者 | 立入禁止エリア、時間帯規制、コマセ(撒き餌)の可否、火気・ドローンの可否、清掃義務 | 港・海岸の公式サイトや現地掲示、管理事務所 |
| 川・湖(内水面) | 都道府県(内水面漁業調整)、漁業協同組合(漁協) | 禁漁区・禁漁期間、サイズ制限、採捕量、釣法制限、遊漁券 | 都道府県の内水面情報、各漁協の公式発表・事務所 |
| 管理釣り場 | 民間事業者・自治体指定管理者 | レギュレーション(バーブレス、フック本数、キャッチ&リリース、ネット・マット必携など) | 施設公式サイト・受付カウンターの掲示 |
海釣り 防波堤 砂浜 磯
海釣りでは、防波堤(波止)、砂浜、磯、漁港内など、エリアごとに立入や釣法が細かく管理されています。港湾や漁港は「作業施設」であるため、釣りが全面的に許可されているわけではありません。砂浜や磯でも、海水浴期間や自然保護の観点から、時間帯や撒き餌の制限、火気の禁止などが設定されることがあります。
漁港での立入禁止エリアと注意点
漁港では、荷さばき地・岸壁の係留区域・漁具置き場・通行帯など、操業や安全確保のため関係者以外立入禁止と明示されるエリアがあります。ロープやワイヤーが張られている場所、作業車両の動線、フォークリフトが往来するエリアは立入禁止と考え、柵・チェーン・黄色黒のバリケード・路面標示・看板などのサインに必ず従ってください。
多くの漁港では、釣り可の岸壁にも条件が付くことがあります(例:指定区域のみ、操業時間帯の利用自粛、夜間立入禁止、ファミリーエリアの分離など)。釣り座を構える前に、管理事務所の掲示や最新のお知らせを確認し、係留船・作業船の離着岸の妨げにならないよう配慮します。足場の悪いテトラ帯や仮設足場は、転落・落水の危険が高く、立入禁止となる場合があります。
照明機材や強力なヘッドライトの使用は、操船者や周辺住民への眩惑・通報の原因となるため、漁港の方針や時間帯ルールに合わせて控えめに運用してください。駐車は指定場所に限り、通行帯や非常口、消火設備の前は避けます。
撒き餌 コマセの扱いと清掃ルール
アミエビやオキアミなどのコマセ(撒き餌)は、漁港・防波堤・海水浴場周辺・養殖いかだ付近で禁止または制限されるケースがあります。特に海水浴場開設期間や、におい・汚れ・鳥の誘引が問題化している場所では、全面禁止や配合餌のみ可など、細かな指定が行われることがあります。現地の掲示で「コマセ禁止」「配合のみ」「遠投カゴ不可」等の記載を確認し、疑義がある場合は管理事務所へ確認します。
清掃は原状回復が原則です。足元にこぼれたコマセは海水とデッキブラシで洗い流し、固形物はネットで回収して持ち帰ります。バッカンやエサ箱の排水をそのまま路面に流すのは嫌悪・悪臭・滑りの原因になります。余ったエサ・アミブロックは海に投棄せず密閉して持ち帰り、糸・仕掛け・パッケージ・氷袋などのプラスチックごみも確実に回収します。風で飛散しやすいごみは重しや袋二重化で管理しましょう。
川や湖など内水面の遊漁規則
内水面(河川・湖沼)では、都道府県が定める内水面漁業調整規則・指示、そして漁業権を持つ漁業協同組合(漁協)の「遊漁規則」が適用されます。アユ・サケ科・コイ科など魚種ごとに、解禁日、禁漁期間、禁漁区、採捕量、サイズ制限、釣法(餌・ルアー・フライ)やエサ種別の制限が設定されるのが一般的です。漁業権が設定されていない水域でも、保護水面や保安上の理由で採捕が制限される場合があるため、必ず公式情報を確認します。
禁漁区 禁漁期間 サイズ制限の確認方法
「魚種」「区間(河川名・河口からの距離・橋梁間)」「期間」「サイズ(全長基準)」「採捕量(日・総量)」を最低限セットで確認すると、現地での迷いが減ります。以下の手順でチェックしましょう。
| 確認項目 | 概要 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 禁漁区 | 堰・魚道周辺、支流合流点、産卵保護区など区間指定。地図・標柱で明示されることが多い。 | 都道府県「内水面」ページ、各漁協の地図・掲示、現地の看板 |
| 禁漁期間・解禁日 | アユやサケ科は年度ごとに期間が設定。早期解禁や臨時休漁の告知に注意。 | 各漁協の年度要項・ポスター、都道府県の告示・指示 |
| サイズ制限・採捕量 | 全長○cm未満のリリース義務、1日の持ち帰り尾数・重量の上限など。 | 漁協の遊漁規則、監視員の案内、遊漁券の裏面記載 |
| 釣法・エサの制限 | ルアー・フライ限定区、餌釣り禁止区、まき餌禁止、トレブルの可否など。 | 区間別レギュレーションの掲示、漁協公式サイト |
工事区間・増水時の立入制限や、ダム・堰堤・取水施設周辺の保安距離も見落としがちです。橋脚の番号、河口からの距離標、堤体から◯mといった区間表示の読み方を事前に把握し、実地で照合できるよう地図を携行します。
遊漁券の購入方法と漁協の窓口
遊漁券(入漁承認証)は、年券・日釣券(半日券設定の場合あり)・現場売りの種別が一般的です。料金や対象魚種は水域ごとに異なり、提示義務があります。監視員による巡回に備え、帽子・ベスト・バッグなど、すぐに取り出せる位置に携帯してください。現場売りは割増設定の地域もあります。
購入先は、各漁協の事務所・指定販売店(釣具店・宿泊施設・ガソリンスタンド等)が中心で、地域によってはオンライン販売やスマホアプリに対応しています。券面や電子券には適用水域・対象魚・有効期間・注意事項が記載されるため、釣行範囲に合致しているか確認しましょう。中学生以下・女性・シニア等の優遇がある地域もありますが、適用条件や身分証提示の要否は事前に各漁協に問い合わせてください。
管理釣り場のルール
管理釣り場(エリアトラウト、管理湖、ルアー・フライ専用ポンド等)は、運営者による詳細なレギュレーションが設定されています。料金区分(男性・女性・ジュニア)、時間券、持ち帰り尾数、エリア分け(ビギナーゾーン、フライ専用区など)、レンタル品の有無が案内されるのが一般的です。施設の掲示・受付説明・配布レギュレーションがすべてに優先します。
バーブレスフック リリース義務 レギュレーション
魚体保護・混雑時の安全確保・トラブル防止のため、バーブレス(スレ)フック・シングルフック指定、キャッチ&リリース義務や、ランディングネット(ラバー製)・リリースマットの推奨・必携が設定されることがあります。写真撮影は短時間で、水からの露出を最小限にし、ぬめり保護のため素手での強い保持や地面置きは避けます。
| レギュレーション例 | 内容 | 主な理由 |
|---|---|---|
| バーブレス・シングル限定 | 返しのないフックを使用。トレブル禁止や1本のみ装着など本数制限あり。 | リリース時のダメージ軽減、混雑時の安全性向上、素早いリリース |
| ルアー・フライ専用 | エサ・撒き餌禁止。ソフトルアー・トレーラー禁止など素材指定あり。 | 水質・景観保全、釣果バランス維持、残渣・匂いの抑制 |
| 持ち帰り尾数・サイズ | 1日◯尾まで、◯cm以上のみ持ち帰り可など。超過は要リリース。 | 放流計画との整合、常連とビジターの公平性確保 |
| ネット・マットの使用 | ラバーネット推奨または必須。地面置き・乾いた手での保持禁止。 | 魚体とヒレの保護、リリース後の生残率向上 |
フックサイズやルアー重量、色(反射やグロー)まで細則がある施設もあります。対岸キャスト禁止、サイトフィッシング時のルール、キープエリアの区分など、細かな取り決めは当日の受付・掲示で最終確認してください。違反は注意・退場の対象となり、次回以降の入場制限を課す施設もあります。
魚種別の保護とサイズ制限
サイズ制限(全長・体長の下限)や禁漁期間・禁漁区は、魚種だけでなく都道府県・水域(海面/内水面)・漁協ごとに異なります。必ず現地の掲示・自治体の漁業調整規則・漁協の遊漁規則を優先して確認してください。
以下では、代表的な内水面(川・湖)の魚種と、海の主要魚を取り上げ、規制の考え方とチェックポイントを整理します。なお、同じ魚種でも地域により法定の採捕禁止サイズや持ち帰り尾数、採捕方法(餌・ルアー・フライ等)の可否が大きく異なるため、数値は一律に示さず確認の方法と実務の注意点を中心に解説します。
アユ ヤマメ イワナ サクラマスの規制
アユやサケ科(ヤマメ・イワナ・サクラマスなど)の多くは、内水面(河川・湖沼)で「内水面漁業調整規則(都道府県)」および各漁協の「遊漁規則」により、禁漁期間・禁漁区・サイズ制限・採捕数制限・採捕方法の制限などが細かく定められています。遊漁券の携帯・提示義務がある水域も一般的です。
| 魚種 | 主な保護の趣旨 | よくある規制の類型 | 確認のポイント |
|---|---|---|---|
| アユ | 遡上資源の保全と産卵親魚の保護、河川ごとの再生産維持 | ・禁漁期間(秋〜冬の産卵期) ・サイズ(全長/体長)下限や採捕数の上限 ・網・ひっかけ・夜間採捕など方法制限 | 解禁日・禁漁期・採捕方法・遊漁券の種類(友釣り/コロガシ等の可否)を水域別に確認 |
| ヤマメ | 渓魚の成熟・産卵期の保護、未成魚の温存 | ・春〜初秋にかけた解禁期設定 ・サイズ下限(全長/体長) ・持ち帰り尾数制限、バーブレス推奨・義務の有無 | 支流・源流の禁漁区、キャッチ&リリース区、ルアー/フライ限定区の有無を確認 |
| イワナ | 成育の遅い高冷地個体群の保護、在来系統の維持 | ・長めの禁漁期間設定 ・サイズ下限と厳しめの尾数制限 ・ストック保護のための区間規制 | 在来保全区の設定や放流魚区分、持ち帰り可否の区間差を地図で確認 |
| サクラマス | 遡上親魚の保護と河川ごとの系群維持 | ・全面禁漁または厳格な期間・区間限定解禁 ・方法制限(餌・ルアー・フライの絞り込み) ・再放流(リリース)義務区の設定 | 「本流/支流」「ダム上/下」で規則が変わる例に注意。標識放流魚の扱いも確認 |
内水面では、同じ河川名でも漁協の管轄が異なるとルールが変わります。看板・公式サイト・地図(区間図)・遊漁券の注意書きを必ずセットで確認し、現地の指示に従ってください。
サイズ表記は「全長」や「体長」など用語が規則で定義されます。計測は平らな面で魚体を真っ直ぐにし、尾鰭の先端(全長の場合は最も後端)までを素早く測り、未達は水温や気温に配慮して即時リリースします。
マダイ ヒラメ キジハタなど海の主要魚の目安
海の主要魚については、都道府県の「海面漁業調整規則」等で、採捕禁止サイズ(全長の下限)、禁漁期間・禁漁区、採捕方法(銛・刺網・投光器等)の可否が定められることがあります。遊漁船や漁港管理者、漁協が自主基準(キープサイズや尾数)を追加で設ける場合もあります。
| 魚種 | 資源特性・保護の狙い | 代表的な規制タイプ | 釣行前チェックと実務の要点 |
|---|---|---|---|
| マダイ | 成熟年齢に達する前の個体を保護し産卵親魚を確保 | ・全長下限制(採捕禁止サイズ) ・産卵期周辺の禁漁区や採捕方法の制限 ・海域別の区分規制 | 都道府県の海面漁業調整規則と、遊漁船・漁協のキープ基準の両方を確認。計測は尾鰭の後端までの全長で統一 |
| ヒラメ | 加入年級の保護と沿岸資源の再生産確保 | ・全長下限制 ・季節・区域の採捕制限(稚魚分布期の保護) ・採捕方法の制限(潜水器具・銛等) | 砂浜・防波堤・磯で規制が違うことがあるためエリア別に確認。全長未達は撮影を手短にし海水で濡らした手で即時リリース |
| キジハタ(アコウ) | 成長が遅く定着性が高い岩礁性資源の保護 | ・全長下限制・尾数制限 ・禁漁区(魚礁・保護区)の設定 ・夜間採捕や投光の可否の制限 | 小型個体・抱卵個体の自主リリースが広く推奨される。根魚は深場での減圧障害にも配慮し迅速な取り込みと海中リリースを徹底 |
海面のサイズ制限は、同一魚種でも隣接県で数値が異なることがあります。漁港や防波堤の掲示、都道府県の告示・規則、遊漁船の船内ルールを必ず事前に照合し、最も厳しい基準に合わせるとトラブルを避けられます。
全長の計測は、魚の吻端から尾鰭の最も後端までをまっすぐ測るのが一般的です。風や波のある釣り場では、耐水メジャーを平置きし、魚体を地面に長く置かない、乾いた手で触れない、必要ショットのみ撮影してすぐに放すなど、資源に配慮した手順を徹底しましょう。さらに、遊漁者の自主基準(法定サイズより余裕を持ってキープしない)を設けると、地域資源の長期的な安定化に寄与します。
外来種とリリース禁止の規則
外来魚の誤ったリリース(再放流)は、生態系の攪乱や在来種の減少につながるため、法律・条例で厳しく禁じられています。本章では、特定外来生物を中心に、釣り人が現場で必ず守るべき禁止事項と適切な取り扱い手順を、最新の制度に合わせて整理します。
制度の基礎は環境省の外来生物法(正式名称:外来生物法・特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で定められており、詳細は環境省の公式解説環境省「外来生物法」総合情報や、種の情報は国立環境研究所「侵入生物データベース」で確認できます。
特定外来生物の持ち込み運搬飼養の禁止
外来生物法では、指定された特定外来生物について、原則として「飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡・野外への放出」などが禁止されています(許可制の例外を除く)。釣りに直接関わる重要ポイントは次のとおりです。
- その場での再放流(キャッチ&リリース)は「野外への放出」に該当し、特定外来生物では禁止です。釣り上げた場所に戻す行為も違反になります。
- 生きたままの移動・持ち帰り(活かしバケツ、ライブウェルでの移送を含む)も原則禁止です。イベントや競技でも同様で、例外許可がない限り行ってはいけません。
- 死亡個体の持ち帰りは法律上の「運搬」には当たりませんが、自治体の廃棄物ルールや漁協の指示に従い、衛生的に処理してください。
また、2023年には条件付特定外来生物(例:アメリカザリガニ、ミシシッピアカミミガメ)が導入され、日常生活への過度な影響を避けながらも野外への放出は厳禁とされています。釣り人にとっては、「野外へ放さない」ことが最重要で、むやみに生体を移送しないという原則に変わりはありません。詳しくは環境省の解説を参照してください。
| 区分 | 主な対象例 | 野外へのリリース | 生きたままの運搬 | 飼養・保管 | 釣り現場での注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定外来生物 | オオクチバス(ブラックバス)、コクチバス、ブルーギル など | 禁止(その場での再放流も不可) | 原則禁止(ライブウェル・活かしバケツ含む) | 原則禁止(研究等の許可制を除く) | 再放流せず、確実に駆除・持ち帰り等。現場の看板や漁協指示に従う |
| 条件付特定外来生物 | アメリカザリガニ、ミシシッピアカミミガメ など | 禁止 | 可能だが、むやみに行わない(地域の指示を優先) | 可能(ただし野外放出は厳禁) | 生体を放さず持ち帰るか、自治体の案内に沿って適切に取り扱う |
なお、都道府県の内水面漁業調整規則や管理者(漁協・公園管理者等)の規定で、法律より厳しい「再放流禁止」「場外持ち出し禁止」などが課される場合があります。釣行前に必ず最新の地域ルールを確認してください。
ブラックバス ブルーギルの取り扱いと回収ボックス
オオクチバス(ブラックバス)、コクチバス、ブルーギルは、環境省が指定する特定外来生物で、国立環境研究所「侵入生物データベース」にも詳細な情報があります。これらの魚種に関する釣り現場での基本対応は次のとおりです。
- 同定(見分け):外来魚か迷う場合は、むやみに移送せず写真を記録して地域の漁協・自治体へ確認を取る。誤同定によるトラブルを避ける。
- 再放流しない:釣った場所に戻す「キャッチ&リリース」は法律上の放出に該当し禁止。同一水域内での移動放流も不可。
- 生かした移送をしない:活かしバケツやライブウェルでの持ち運び、車両や船での生体移送は行わない。
- 適切な処理:食用に持ち帰る場合は氷締め等で速やかに鮮度管理。廃棄する場合は自治体の廃棄物ルールに従い、密封の上で家庭ごみへ出すなど衛生的に処理(現場投棄は厳禁)。
- 回収ボックスの活用:琵琶湖周辺など一部地域では「外来魚回収ボックス」等が設置されています。設置場所や利用方法は自治体・漁協の案内に従い、指定がない場所へ勝手に投棄しない。
大会やイベントでの扱いについても、生体の持ち運びを伴う方式は外来生物法に抵触するおそれがあるため、必ず主催者が法令・許可・自治体規定を確認し、重量計測等は生体移送を伴わない方法へ改めるなど、法令順守の体制をとる必要があります。
ブラックバスやブルーギルが釣れやすい内水面では、漁協・河川管理者が独自の駆除方針や回収体制を示していることがあります。現地の看板・漁協の掲示・公式サイトの告知を優先し、不明点は事前に問い合わせてから入釣してください。制度の概要は環境省「外来生物法」で確認できます。なお、地域の条例・規則違反や外来生物法違反が確認された場合は、行政指導や罰則の対象となり得ます。
まとめると、外来魚対策の最優先事項は「野外に放さない」「生体を移送しない」「地域の指示に従う」の3点です。釣り人一人ひとりの適切な行動が在来生態系の保全につながります。
道具と行為の禁止事項
この章では、全国共通で法令により禁止される道具・行為と、都道府県の漁業調整規則や管理者のローカルルールによって制限される事項を、実務目線で整理します。釣り場の管理主体(都道府県、漁協、漁港・港湾管理者、公園・河川管理者、管理釣り場)はそれぞれ別で、同じ道具でもフィールドにより可否が逆転することがあります。
全国一律の法令で明確に禁じられているものは絶対に使用しないこと、ローカルルールは釣行前に原文(公式告示・規則、現地掲示、管理者サイト等)で確認しましょう。なお、最新のガイドや制度の入口情報は水産庁公式サイトを参照して、該当都道府県・管理者ページへたどるのが実務的です。
水中銃 ドローン釣り 投光器の可否
ここでは、問い合わせが多く、トラブルになりやすい三つのトピックを要点整理します。いずれも「全国法令の原則」→「現地規則」→「安全・環境配慮」という順に判断してください。
水中銃(水中で魚を撃つ器具)
水中銃(魚銃)は、一般の所持・譲渡・携帯が法令で原則禁止とされる代表例です。遊漁目的の使用はもちろん不可です。さらに、潜水器具(スキューバ等)を用いた採捕は、都道府県の海面漁業調整規則で広範に禁止または厳しく制限されています。水中銃の所持・使用はしない、潜水採捕は許可・規則の有無を原文で確認するが大原則です。
ドローン釣り(無人航空機からの仕掛け投入・回収)
ドローン(無人航空機)の運用は航空法等の対象で、人口集中地区、空港周辺、夜間、目視外、第三者または物件からの距離などに厳格なルールがあり、物件投下(ルアーや仕掛けの投下に相当)も原則禁止で、運用には許可・承認が必要となる場合があります。許可の可否はルールに適合しても現地管理者の禁止で運用できないことが多く、漁港や港湾、公園・海岸は管理規則でドローン自体が禁止のケースが一般的です。
手続き・申請の入口は国土交通省DIPSポータルを確認し、航空法の適法性と現地(港湾・公園・漁協等)の禁止事項の両方を満たさない限り、ドローン釣りは実務上「できない」と判断するのが安全です。
投光器・集魚灯(夜間の強力照明)
夜間の強力な投光器や集魚灯は、海面・内水面いずれも都道府県の漁業調整規則で禁止や光量・用途の制限対象になることが多く、遊漁では原則不可または厳格な制限が一般的です。航行や周辺住民の迷惑、プランクトン異常発生、生態・鳥類への影響が理由です。
安全確保のためのヘッドランプや足元灯と、魚群を寄せる目的の集魚灯は法的・運用上の扱いが異なるため、「保安用の最小限照明」にとどめ、発電機や高出力ライトで海面を広範囲に照らす行為は避けるのが無難です。
| 道具・行為 | 全国的な原則 | 現地での典型的な扱い | 要確認の管理主体 |
|---|---|---|---|
| 水中銃(魚銃) | 所持・使用とも原則禁止 | 禁止が一般的。潜水採捕も多くの県規則で禁止/制限 | 都道府県(海面漁業調整規則)、警察 |
| ドローン釣り | 航空法等により厳格な運用制限。物件投下は原則不可 | 漁港・港湾・公園等で管理者が禁止するケース多数 | 国土交通省(航空法・DIPS)、港湾/公園管理者、漁協 |
| 投光器・集魚灯 | 集魚目的の強力照明は規制対象になりやすい | 海面・内水面とも禁止または光量・用途制限が一般的 | 都道府県(海/内水面規則)、港湾管理者、河川/公園管理者 |
トレブルフック 使用本数 撒き餌の規制
釣り針や仕掛けの仕様、撒き餌の可否は「フィールド別・魚種別・時期別」に細かく分かれます。とくに内水面(川・湖・ダム・貯水池)は漁協が定める遊漁規則で詳細が決まり、海では都道府県の海面漁業調整規則や漁港管理者のローカルルールが優先します。
- 針の形状(トレブル/シングル/バーブレス)
- 針数(総本数)
- 竿数
- 撒き餌・コマセの持ち込み量・禁止水域
の4点は毎回チェックしましょう。
トレブルフックの扱い
海のショア・オフショアではトレブルフック自体は原則として合法ですが、海鳥被害や他者との接触リスク、回収困難な根掛かりが多い場では管理者が禁止・制限することがあります。内水面では、外来魚対策やリリース前提の魚種保護のため、トレブル禁止・バーブレス限定を採る漁協や管理釣り場が一般的です。大会・イベントでは独自レギュレーションが設定されます。
使用本数(針数)・竿数の上限
内水面の遊漁規則では、一人あたりの「総針数」や「同時に出せる竿数」の上限が定められているのが通例です(例:同時に2本竿まで、総針数10本まで等)。海でもサケ・マス等の保護対象や特定区域では、はえ縄・多点針・ぎょりん仕掛け等が禁止されることがあります。違反は没収・退去のほか、行政指導や罰則対象になるため、道具を用意する前に「本数上限」と「禁止仕掛け」を現地規則で特定してください。
撒き餌・コマセ(配合エサ・生エサ)の規制
湖沼・ダムでは水質保全の観点からコマセ使用禁止や量・配合制限が普及しています。海でも漁港内や遊泳区域近接、水産物取扱区域では、撒き餌禁止・洗い場指定・清掃義務が定められることがあります。乾燥配合・生エサともに持ち込み制限がある場合があるため、購入前に現地ルールの確認が必須です。使用後は残餌・パッケージを必ず持ち帰り、岸壁・駐車場を洗い流す必要がある区域では規定に従い清掃を実施します。
| 項目 | 海(防波堤・磯・船) | 内水面(川・湖・ダム) | 管理釣り場 | 確認先の例 |
|---|---|---|---|---|
| トレブルフック | 原則可。区域・対象魚・混雑状況で禁止/制限あり | 禁止やバーブレス限定が多い | 施設レギュレーションで可否明記(バーブレス限定が通例) | 都道府県海面規則、漁港管理者、漁協告示 |
| 針数・竿数 | 区域・魚種により上限あり。多点針・はえ縄系は不可が多い | 総針数・同時竿数の上限を明確に規定するのが一般的 | 台数・針数を細かく指定 | 漁協の遊漁規則、都道府県内水面規則 |
| 撒き餌・コマセ | 港内・遊泳区域近接・取扱区域で禁止や清掃義務 | 水質保全で禁止/量制限が普及 | 全面禁止または種類・量を指定 | 港湾・公園管理者、漁協、施設規約 |
なお、全国的に共通して、爆発物・毒物・麻酔剤・電気ショック等、生物・人身・環境に重大な危険を及ぼす道具・方法は法令で厳格に禁止されています。これらは「知らなかった」で済まない重大違反に直結します。疑義がある道具・方法は使用前に必ず管理者へ問い合わせ、代替手段(安全装備の充実、光量を落とす、シングル・バーブレスへの変更、コマセ不使用の釣法に切り替える等)を選択してください。
釣り船と遊漁船のルール
釣行で船を利用する際は、事業者・乗客の双方が守るべき法令と安全ルールがあります。本章では、遊漁船(乗合船・仕立船)を利用する前に必ず押さえておきたい「法的枠組み」と「乗船時の安全・補償」の要点を、実務での確認ポイントとともに整理します。登録済みの事業者か、定員・安全装備・着用ルールが適正かを事前に確認し、当日は船長の指示に従うことが、事故防止とトラブル回避の最短ルートです。
遊漁船業の適正化に関する法律のポイント
遊漁船(釣り船)で有償のサービスを提供する事業は、「遊漁船業の適正化に関する法律」(所管:水産庁)により運用の基本が定められ、都道府県の制度に基づく手続・表示・安全管理のルールが適用されます。制度の最新情報や運用の解説は水産庁の公式情報(水産庁)で確認できます。
実際の釣行では、予約・受付の段階で「事業者情報の表示」「料金やキャンセル規定の明示」「安全に関する説明」などが提供されます。船内では、検査で定められた「最大搭載人員(定員)」の範囲内で運航され、定員超過は認められません(検査・定員の考え方は日本小型船舶検査機構(JCI)の案内が参考になります)。
| 用語 | 概要 | 料金の考え方 | よくある運用 | 注意すべきルール |
|---|---|---|---|---|
| 乗合船 | 複数の利用者が相乗りする一般的な遊漁船の形態 | 1人あたりの乗船料+氷・餌等の実費 | 出船時刻・釣り座の割当・ターゲット魚種が事業者指定 | 集合時間厳守、釣り座移動は船長の許可に従う、船内ルールに従って仕掛け・コマセを使用 |
| 仕立船(チャーター) | 1グループで貸切る形態 | 船1隻あたりの料金(人数上限は定員内) | 出船時間・釣り物・釣り方の調整がしやすい | 定員厳守、海況次第で船長が釣り場や帰港を判断、器物損壊・迷惑行為の禁止 |
乗船前に見るべき掲示・書類の代表例は次のとおりです。不明点はその場で質問し、約款・注意事項・中止基準を事前に把握しておきましょう。
| 項目 | 確認できる場所 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 事業者情報の表示 | 受付・船内掲示・公式サイト | 事業者名・連絡先、営業エリア、注意事項の明示 |
| 料金・キャンセル規定 | 予約時の案内・サイト・掲示 | 料金に含まれるもの(氷・餌・仕掛け)、中止時/自己都合時の取り扱い |
| 最大搭載人員(定員) | 船内掲示・検査関係書類の写し | 定員超過の乗船は不可、幼児の扱いも含め人数計算を厳密に |
| 安全に関する案内 | 乗船前ブリーフィング・掲示 | 救命胴衣の着用ルール、避難方法、立入禁止区画 |
なお、遊漁船の運航は海上交通や安全の観点から、国土交通省・海上保安庁の指導にもとづく安全対策が求められます。航行や救助、安全啓発の情報は海上保安庁の案内が参考になります。
乗船時の安全装備と保険
小型船舶では、航行区域・船種に応じて法令で定められた救命・消防・信号などの装備を備えます。乗客に関わる最重要事項は救命胴衣(ライフジャケット)の着用です。国のルールに基づき、原則として航行中は国土交通省の型式承認(いわゆる「桜マーク」)が付いた救命胴衣の着用が求められます。詳細な着用場面や例外は地域・船種・運用で異なるため、当日の船長の指示に従ってください(安全情報は海上保安庁の案内を参照)。
船はJCIの検査に適合したうえで、検査証書・検査手帳に記載された航行区域・定員・装備の範囲で運航します。乗客は定員厳守、立入禁止区画への進入禁止、移動時の手摺保持(3点支持)などの基本動作を徹底し、危険な投げ釣り・オーバーヘッドキャスト・船上での走行・過度な飲酒など事故につながる行為を避けます(検査・装備の基本は日本小型船舶検査機構で確認できます)。
| 代表的な安全装備 | 具体例 | 乗客が守ること |
|---|---|---|
| 救命設備 | 救命胴衣(型式承認品)、救命浮環 | 常時着用、サイズ/股ベルト調整、救命具の保管場所を把握 |
| 信号用具 | 信号紅炎・発煙筒等 | 勝手に触れない、保管場所の案内のみ把握 |
| 消防設備 | 消火器等 | 通路・設置場所を塞がない、火気の使用は船長の指示に従う |
| 通信・位置情報 | 無線・携帯・航海計器 | 緊急時は船長の指示で通報、機器には触れない |
| 甲板安全 | 手摺・滑り止め・救命はしご | 移動は低姿勢で3点支持、濡れた甲板での走行禁止 |
安全運航のため、出船可否は天候・海況・視程・潮流・運航計画などを踏まえ船長が判断します。警報・注意報や急な時化で計画変更・中止となることもあるため、前日・当日の連絡手段を確保し、集合時刻・乗船場所・駐車ルール・持参装備(長靴・レインウエア・酔い止めなど)を確実に準備してください。
補償・保険については、事業者ごとに加入状況や補償範囲が異なります。一般に、事業者の賠償責任保険、乗客個人のレジャー保険・傷害保険などが検討対象となります。次の点を予約時に確認すると安心です。
| 確認事項 | 見るべきポイント | 問い合わせ例 |
|---|---|---|
| 事業者の保険加入 | 対人・対物の賠償範囲、支払限度額、適用除外 | 船上の転倒・針刺し・落水などは補償対象か |
| 個人の任意保険 | 釣り・船釣りを対象に含むか、救援者費用の有無 | 自分のタックル破損・盗難は対象か |
| 中止・返金条件 | 天候中止時の返金・振替、自己都合キャンセル料 | 集合後の急変で早上がりの扱い |
最後に、受付では氏名や連絡先を記入する乗船名簿の提出を求められることがあります。これは安全管理と連絡体制のための運用であり、記載事項は正確に伝えましょう。法令・行政の最新情報は、水産庁・海上保安庁・検査機関の公式情報を定期的に確認し、地域や事業者の掲示に従ってアップデートすることが大切です(参考:水産庁/海上保安庁/日本小型船舶検査機構)。
現地トラブルを避けるためのマナーと罰則
釣り場でのトラブルは、規則そのものの違反よりも、駐車・ゴミ・騒音・立入禁止の無視といった「基本のマナー」から発生することが多く、結果的に釣り場の閉鎖や取締り強化につながります。地域のローカルルールや管理者の指示に沿って行動し、周囲の生活や操業、環境保全に最大限の配慮をすることが、快適で安全な釣行への近道です。
駐車 ゴミ持ち帰り 近隣配慮の実践
現地の注意喚起看板や標識、漁協・管理者の案内は「その場所で過去に起きたトラブル」の反映です。標識やロープ・バリケード・カラーコーンで明示された立入禁止や駐停車禁止は必ず守り、満車時は時間帯をずらす・相乗りする・有料駐車場を使うなど、周辺交通の安全を最優先にします。
ゴミは全て持ち帰りが大原則です。特にコマセ袋・パッケージ・切れたラインやフックは海洋ごみ化・野生動物の誤食・事故の原因になります。環境省も海洋プラスチック問題への対策を呼びかけています(環境省:海洋ごみ・プラスチック対策)。臭い対策として耐臭ゴミ袋や密閉コンテナを携行し、ラインの端材は短く切ってから収納すると安全です。
深夜・早朝は生活圏と隣接するポイントが多く、エンジンのかけっぱなし、大声、ドアの開閉音、高照度ライトの多用は苦情の種になります。ライトは足元と手元中心に絞り、他者や民家、航行船舶へ向けないのが基本です。片付け時の洗い流しは、指定の水場がない場所では行わず、血抜き水やコマセ残渣を側溝・用水路へ流さないでください。
釣り座では、先行者のキャスト方向・風向・潮流に合わせ、割り込みや横切りキャスト、コマセの風下被りを避けます。タモ入れや取り込み時は一声かけて協力し合い、トラブルの芽を摘むことが重要です。
| シーン | NG行為 | 想定されるトラブル・リスク | 実践策(推奨行動) |
|---|---|---|---|
| 駐車・乗降 | 路上駐車・私有地や漁業者通路の占有 | 通行妨害、通報・撤去、釣り場の閉鎖 | 公式駐車場の利用、満車時は時間変更や相乗り、荷下ろしは短時間・同乗者がすぐ移動 |
| ゴミ・残餌 | コマセ袋やライン・フックのポイ捨て、残餌の放置 | 野生動物の誤食・怪我、景観悪化、清掃負担の増大 | 全量持ち帰り、耐臭袋と小型はさみを携行、残餌は密閉容器へ回収 |
| 騒音・光害 | 深夜の大声・ドア音・大音量、強いライトの照射 | 近隣からの苦情、巡回強化、立入規制 | 会話は控えめ、スライドドアは手添えで静かに、ライトは足元限定で低照度に調整 |
| 釣り座の共有 | 割り込み、横切りキャスト、コマセが他者にかかる | 口論・接触事故、通報・退去要請 | 先行者に一声、キャスト方向の確認、タモ入れ協力と順番待ち |
| 清掃・退出 | 海水・血抜き水の無断放流、床面の汚れ放置 | 悪臭・滑り事故、管理者からのクレーム | 拭き取りと持ち帰りを徹底、指定の水場がない場所では洗い流しをしない |
「少しでも迷惑になりそう」と感じた行為はやめる・減らす・時間をずらす——この三原則を徹底すれば、多くの現地トラブルは未然に防げます。
違反の罰金 行政指導 送致事例
釣り場の問題行為は、現場の管理者(漁港管理者、漁協、市区町村など)や警察・海上保安庁により、口頭注意から退去要請、再発時の通報といった段階的な対応が取られるのが一般的です。内容や悪質性によっては、各種条例による過料・指導、道路交通法の反則金・レッカー移動、廃棄物の不適正処理に関する法令違反、立入禁止の無視に対する検挙など、法的措置に発展する場合があります。海辺での事故・危険を発見した際は、海上保安庁の緊急通報「118番」に連絡します(海上保安庁 公式サイト)。
以下は、現地で起こりがちな行為と、想定される処分類型・予防ポイントの整理です。実際の適用法令や金額・手続は地域・状況により異なるため、現地の表示・担当窓口の指示に従ってください。
| 行為の例 | 主なリスク・処分類型の例 | 現場での初動 | 予防のポイント |
|---|---|---|---|
| 路上駐車・迷惑駐車 | 反則金・レッカー移動、近隣からの通報、釣り場の閉鎖 | 直ちに移動・退去、管理者や警察の指示に従う | 駐車場の事前確認、相乗り・時間調整、荷下ろしは短時間で |
| 立入禁止の無視(防波堤・施設内) | 管理者による退去要請・通報、検挙の可能性 | 指示に即時従い、再入場しない。表示や告示を撮影して次回に備える | 最新の規制表示を現地で再確認、封鎖箇所には近づかない |
| ゴミの投棄・残餌の放置 | 条例による過料、悪質な不法投棄は厳しい処分の対象になり得る | 回収・清掃を行い、管理者に謝意と再発防止を伝える | 耐臭袋と清掃用具を常備、持ち帰りを徹底 |
| 器物損壊・設備の不適切使用 | 賠償請求・通報、出禁・閉鎖の引き金 | 弁済・修繕の協議、指示に従い退去 | 施設は共同利用の前提で丁寧に扱う。私物化しない |
| 口論・威圧的言動 | 通報・警察対応、最悪の場合は送致 | 距離を取り、相手を撮影・ネット投稿しない。第三者を交えて解決 | 先行者優先と一声の徹底、譲り合いと時間調整 |
実際には、駐車や立入に関するトラブルが再三続くと、管理者がエリア自体を封鎖する、あるいは釣り禁止の告示を行うことがあり、地域コミュニティや他の釣り人に長期的な不利益が生じます。注意を受けたら反論よりもまず従い、その場で収める——その判断が、トラブルの拡大と送致を防ぐ最善策です。
迷ったときは「表示・ルールを確認し、管理者に問い合わせ、無理をしない」という基本に立ち返りましょう。安全確保や環境保全に関わる事項は、最優先で配慮する姿勢が求められます。
47都道府県の規則リンクと調べ方
釣行前に必ず公的情報(都道府県の例規集・告示・担当課ページ・漁協の案内)で最新の禁止事項・禁漁期間・体長制限・立入禁止の有無を確認し、SNSや個人ブログの情報だけで判断しないことが、安全かつ合法的な釣りの第一歩です。ここでは、都道府県ごとの検索キーワード例と窓口の見つけ方、問い合わせのコツをまとめます。
公式サイトでの検索キーワード例
まずは都道府県名に続けて、正式名称に近い語で検索します。特に「内水面漁業調整規則」「海面漁業調整規則」「遊漁」「禁漁期間」「採捕禁止」「遊漁券」「漁業調整委員会」「例規集」「告示」「漁港 立入禁止」「自然公園 特別保護地区」といった語が役立ちます。精度を上げるにはダブルクォーテーション(完全一致)や、filetype:pdf、site:lg.jp などの検索演算子も有効です。
| 用途 | 推奨キーワード例 | 検索のコツ・補足 |
|---|---|---|
| 海釣りの規則全般 | 「都道府県名 海面漁業調整規則」「都道府県名 海釣り 禁止」「都道府県名 漁港 立入禁止」 | 「告示」「PDF」を足すと正式文書に当たりやすい。港湾・漁港の立入は管理者ページに掲載されることが多い。 |
| 川・湖の遊漁規則 | 「都道府県名 内水面漁業調整規則」「都道府県名 遊漁券 販売」「都道府県名 禁漁期間 アユ」 | 「漁協名」を足すと、遊漁券やレギュレーションの最新情報に絞れる。 |
| エリアの立入・行為制限 | 「都道府県名 自然公園 特別保護地区」「都道府県名 鳥獣保護区 行為制限」「都道府県名 河川 立入禁止」 | 自然公園や保護区は環境部局、河川・港湾は管理者(河川課・港湾課)のページが一次情報。 |
| 正式名称の確認 | 「都道府県名 例規集 漁業」「都道府県名 漁業調整委員会 告示」 | 例規集は条例・規則の正式名称や最新改正日を確認するのに最適。 |
以下の一覧は、47都道府県ごとに「まず試すべき検索語」と「想定される所管(例)」を示したものです。各所管名は自治体により表記が異なるため、ページ内で「水産課」「水産振興課」「農林水産部」「港湾課」「河川課」「環境政策課」などを目印にしてください。
| 都道府県 | 主な公式用語(検索語例) | 所管部局(例) | 参考トピック(例) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 「北海道 海面漁業調整規則」「北海道 内水面漁業調整規則」「北海道 遊漁 禁漁」 | 水産課/水産振興課 | 禁漁期間・採捕禁止・サイズ制限 |
| 青森県 | 「青森県 海面漁業調整規則」「青森県 内水面漁業調整規則」「青森県 漁港 立入禁止」 | 水産課 | 漁港での釣り可否・清掃ルール |
| 岩手県 | 「岩手県 海面漁業調整規則」「岩手県 内水面漁業調整規則」「岩手県 遊漁券」 | 水産振興課 | 禁漁区・遊漁承認 |
| 宮城県 | 「宮城県 海面漁業調整規則」「宮城県 内水面漁業調整規則」「宮城県 釣り 禁止区域」 | 水産業担当課 | 港湾・防波堤の立入情報 |
| 秋田県 | 「秋田県 海面漁業調整規則」「秋田県 内水面漁業調整規則」「秋田県 禁漁期間」 | 水産振興課 | 河川の禁漁区・期間 |
| 山形県 | 「山形県 海面漁業調整規則」「山形県 内水面漁業調整規則」「山形県 漁港 釣り」 | 水産課 | 体長制限・採捕禁止 |
| 福島県 | 「福島県 海面漁業調整規則」「福島県 内水面漁業調整規則」「福島県 遊漁券 販売」 | 水産課 | 遊漁券とレギュレーション |
| 茨城県 | 「茨城県 海面漁業調整規則」「茨城県 内水面漁業調整規則」「茨城県 釣り 立入禁止」 | 水産振興課 | 港湾・河川の禁止事項 |
| 栃木県(内水面) | 「栃木県 内水面漁業調整規則」「栃木県 遊漁券」「栃木県 禁漁期間」 | 内水面担当課 | サイズ制限・採捕禁止 |
| 群馬県(内水面) | 「群馬県 内水面漁業調整規則」「群馬県 遊漁券」「群馬県 禁漁区」 | 内水面担当課 | 渓流の解禁・禁漁 |
| 埼玉県(内水面) | 「埼玉県 内水面漁業調整規則」「埼玉県 遊漁券 販売」「埼玉県 釣り 禁止」 | 水産・農林部門 | 河川の採捕制限 |
| 千葉県 | 「千葉県 海面漁業調整規則」「千葉県 内水面漁業調整規則」「千葉県 漁港 釣り 可否」 | 水産課/水産振興課 | 港湾の立入ルール |
| 東京都 | 「東京都 海面漁業調整規則」「東京都 内水面漁業調整規則」「東京都 釣り 禁止区域」 | 水産担当部署 | 防波堤・河川利用 |
| 神奈川県 | 「神奈川県 海面漁業調整規則」「神奈川県 内水面漁業調整規則」「神奈川県 漁港 立入禁止」 | 水産課 | コマセ・清掃ルール |
| 新潟県 | 「新潟県 海面漁業調整規則」「新潟県 内水面漁業調整規則」「新潟県 禁漁期間」 | 水産振興課 | 河川・海面の採捕制限 |
| 富山県 | 「富山県 海面漁業調整規則」「富山県 内水面漁業調整規則」「富山県 釣り 禁止」 | 水産課 | 立入禁止・サイズ制限 |
| 石川県 | 「石川県 海面漁業調整規則」「石川県 内水面漁業調整規則」「石川県 漁港 釣り」 | 水産課 | 港湾の安全管理 |
| 福井県 | 「福井県 海面漁業調整規則」「福井県 内水面漁業調整規則」「福井県 禁漁区」 | 水産課 | 禁漁・採捕禁止種 |
| 山梨県(内水面) | 「山梨県 内水面漁業調整規則」「山梨県 遊漁券」「山梨県 禁漁期間」 | 内水面担当課 | 湖沼の遊漁規則 |
| 長野県(内水面) | 「長野県 内水面漁業調整規則」「長野県 遊漁券」「長野県 渓流 解禁」 | 内水面担当課 | 渓流魚の体長制限 |
| 岐阜県(内水面) | 「岐阜県 内水面漁業調整規則」「岐阜県 遊漁券」「岐阜県 禁漁区」 | 内水面担当課 | 郡上・飛騨の河川規則 |
| 静岡県 | 「静岡県 海面漁業調整規則」「静岡県 内水面漁業調整規則」「静岡県 漁港 立入禁止」 | 水産・港湾担当 | 港湾・防波堤の可否 |
| 愛知県 | 「愛知県 海面漁業調整規則」「愛知県 内水面漁業調整規則」「愛知県 釣り 禁止区域」 | 水産課 | 河口域・港湾のルール |
| 三重県 | 「三重県 海面漁業調整規則」「三重県 内水面漁業調整規則」「三重県 禁漁期間」 | 水産振興課 | 採捕禁止・遊漁承認 |
| 滋賀県(内水面・琵琶湖) | 「滋賀県 内水面漁業調整規則」「滋賀県 琵琶湖 遊漁」「滋賀県 禁漁期間」 | 内水面担当課 | 琵琶湖の特有ルール |
| 京都府 | 「京都府 海面漁業調整規則」「京都府 内水面漁業調整規則」「京都府 漁港 釣り」 | 水産課 | 日本海側の港湾ルール |
| 大阪府 | 「大阪府 海面漁業調整規則」「大阪府 内水面漁業調整規則」「大阪府 釣り 立入禁止」 | 水産・港湾担当 | 湾岸部の安全・禁止 |
| 兵庫県 | 「兵庫県 海面漁業調整規則」「兵庫県 内水面漁業調整規則」「兵庫県 漁港 釣り」 | 水産課 | 瀬戸内・日本海の両海面 |
| 奈良県(内水面) | 「奈良県 内水面漁業調整規則」「奈良県 遊漁券」「奈良県 禁漁区」 | 内水面担当課 | 山間河川の規則 |
| 和歌山県 | 「和歌山県 海面漁業調整規則」「和歌山県 内水面漁業調整規則」「和歌山県 釣り 禁止」 | 水産課 | 磯・港湾の立入情報 |
| 鳥取県 | 「鳥取県 海面漁業調整規則」「鳥取県 内水面漁業調整規則」「鳥取県 漁港 立入禁止」 | 水産課 | 港湾の安全確保 |
| 島根県 | 「島根県 海面漁業調整規則」「島根県 内水面漁業調整規則」「島根県 禁漁期間」 | 水産課 | 沿岸の採捕制限 |
| 岡山県 | 「岡山県 海面漁業調整規則」「岡山県 内水面漁業調整規則」「岡山県 漁港 釣り」 | 水産課 | 瀬戸内の立入ルール |
| 広島県 | 「広島県 海面漁業調整規則」「広島県 内水面漁業調整規則」「広島県 釣り 禁止」 | 水産課 | 島しょ部の港湾情報 |
| 山口県 | 「山口県 海面漁業調整規則」「山口県 内水面漁業調整規則」「山口県 漁港 立入禁止」 | 水産課 | 日本海・瀬戸内の両海面 |
| 徳島県 | 「徳島県 海面漁業調整規則」「徳島県 内水面漁業調整規則」「徳島県 禁漁期間」 | 水産課 | 河口域の採捕制限 |
| 香川県 | 「香川県 海面漁業調整規則」「香川県 内水面漁業調整規則」「香川県 漁港 釣り」 | 水産課 | 瀬戸内のサイズ制限 |
| 愛媛県 | 「愛媛県 海面漁業調整規則」「愛媛県 内水面漁業調整規則」「愛媛県 釣り 禁止」 | 水産課 | 沿岸・内湾のルール |
| 高知県 | 「高知県 海面漁業調整規則」「高知県 内水面漁業調整規則」「高知県 漁港 立入禁止」 | 水産課 | 磯場での安全と禁止 |
| 福岡県 | 「福岡県 海面漁業調整規則」「福岡県 内水面漁業調整規則」「福岡県 漁港 釣り」 | 水産課 | 湾岸・港湾の可否 |
| 佐賀県 | 「佐賀県 海面漁業調整規則」「佐賀県 内水面漁業調整規則」「佐賀県 禁漁期間」 | 水産課 | 有明海沿岸のルール |
| 長崎県 | 「長崎県 海面漁業調整規則」「長崎県 内水面漁業調整規則」「長崎県 漁港 立入禁止」 | 水産課 | 離島部の港湾情報 |
| 熊本県 | 「熊本県 海面漁業調整規則」「熊本県 内水面漁業調整規則」「熊本県 釣り 禁止」 | 水産課 | 内湾・干潟の採捕制限 |
| 大分県 | 「大分県 海面漁業調整規則」「大分県 内水面漁業調整規則」「大分県 漁港 釣り」 | 水産課 | 湾岸の安全・禁止 |
| 宮崎県 | 「宮崎県 海面漁業調整規則」「宮崎県 内水面漁業調整規則」「宮崎県 禁漁区」 | 水産課 | 沿岸・河川の規則 |
| 鹿児島県 | 「鹿児島県 海面漁業調整規則」「鹿児島県 内水面漁業調整規則」「鹿児島県 漁港 立入禁止」 | 水産課 | 離島・湾のルール |
| 沖縄県 | 「沖縄県 海面漁業調整規則」「沖縄県 内水面漁業調整規則」「沖縄県 釣り 禁止」 | 水産課 | サンゴ礁域の配慮事項 |
検索結果で「例規集(条例・規則集)」が見つかったら、改正履歴と施行日を確認し、現行条文を必ず確認します。港湾や漁港の「立入禁止」や「釣り禁止」は、管理者のページや現地掲示で更新されやすいため、二次情報ではなく一次情報に当たることが重要です。
漁協や管理者への問い合わせ手順
不明点が残る場合は、都道府県の担当課や漁業協同組合、港湾・河川の管理者に確認します。以下の流れで行うと、確認漏れを防げます。
- 前提整理:釣行予定日、場所(水域の正式名称・区間)、対象魚種、釣法(エサ・ルアー・フライ等)、採捕の有無(持ち帰り/完全リリース)をメモ化。
- 一次情報の確認:都道府県名+「内水面漁業調整規則/海面漁業調整規則」「例規集」「告示」で最新条文と告示を確認。必要に応じて「filetype:pdf」を併用。
- 担当課に問い合わせ:水産課等の代表電話・メールに、上記の前提と「禁漁期間・サイズ制限・採捕禁止種・釣法制限・区域指定」の可否を質問。可能なら条文や告示の該当箇所URLを併記して確認。
- 内水面は漁協にも確認:遊漁券の要否・販売場所・当日の監視体制・リリース規定など、現地運用の詳細は漁協が最も詳しい。
- 港湾・漁港・河川の占用・立入は管理者へ:柵内・防波堤先端・船溜まり等の立入可否は港湾管理者、河口域や護岸工事区間の制限は河川管理者に確認。
- 保護地域の行為制限は環境部局:自然公園(特別保護地区等)や鳥獣保護区は、対象行為(採捕・持込・いそがき等)の可否を確認。
- 現地掲示で最終確認:臨時の立入禁止や工事による区間閉鎖は告知板が最速。矛盾があれば掲示を最優先し、後で管理者に報告・確認。
- 回答は日時・担当部署・氏名(可能な範囲)を記録し、メールや文書で保管することで、現地でのトラブル予防と再確認が容易になります。
| 問い合わせ先 | 主な役割 | 確認できる事項の例 |
|---|---|---|
| 都道府県 水産課・水産振興課 等 | 海面・内水面の規則の所管、告示・例規の案内 | 禁漁期間、体長制限、採捕禁止種、区域指定、漁業調整委員会情報 |
| 内水面漁業協同組合(漁協) | 遊漁券発行、現場運用の管理 | 遊漁券の要否・価格・購入場所、区間レギュレーション、リリース規定、監視体制 |
| 港湾・漁港管理者(港湾課 等) | 施設管理、立入禁止・危険箇所の指定 | 防波堤・岸壁の釣り可否、立入禁止区画、夜間立入、清掃・撒き餌の扱い |
| 河川管理者(県土整備・河川課 等) | 河川法に基づく占用・工事・立入の管理 | 工事区間の閉鎖、護岸での禁止、流域の占用許可の要否 |
| 環境部局(自然保護・公園課 等) | 自然公園・保護区の行為制限 | 特別保護地区での採捕可否、動植物の持込・放流の禁止事項 |
| 管理釣り場(運営者) | 施設独自のレギュレーション | バーブレス義務、持ち帰り枠、ルアー制限、フック規定 |
電話が繋がりにくい場合は、問い合わせフォームやメールの利用が有効です。問い合わせ文には「場所・魚種・釣法・日時・確認したい項目」を箇条書きし、関連ページのURL(例規集・告示・漁協案内)があれば併記すると正確な回答に繋がります。
よくある質問
夜釣りは何時まで可能か
夜釣りの可否や時間帯の制限は、フィールドの種別(海・河川・湖沼・管理釣り場など)と、その場所を管理する行政・施設管理者・漁協等の規約によって異なります。 一般の海岸や砂浜のように24時間立入りそのものは自由な場所もあれば、漁港・防波堤・公園型の釣り施設のように開閉門時間や立入禁止時間が決められている場所、内水面(河川・湖沼)のように魚種保護や安全確保の観点から夜間の採捕を制限する区域があります。
最終的には「現地の標識・掲示・ライン(ロープやチェーン)」が最優先のルールです。 オンライン情報や口コミと異なる掲示を見かけたら、掲示の内容に従ってください。特に漁港では、荷役中エリア・船舶出入り口・立入禁止柵の内側は終日立入禁止が基本です。
| フィールド | 主な規制・確認ポイント | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 防波堤・漁港(海) | ゲート開閉時間、夜間立入禁止区画、荷役エリア、立入禁止標識、照明の使用マナー(船舶の視認を妨げない) | 港湾管理者・漁港の掲示、自治体サイト、現地の管理詰所 |
| 砂浜・海岸 | 迷惑防止条例に基づく深夜の騒音・照明自粛、車両の進入禁止時間、海岸清掃・ゴミ持ち帰り | 市区町村の海岸管理部署、現地表示 |
| 磯・岩場 | 高潮・高波・うねり時の立入自粛、国立・国定公園なら自然公園法に基づく区域規制、転落危険箇所 | 公園管理者、都道府県の自然保護課、現地表示 |
| 河川(内水面) | 内水面漁業調整規則の禁漁区・禁漁期間・採捕時間帯、遊漁券の必要性、夜間照明の使用制限 | 各都道府県の内水面漁業調整規則(e-Gov法令検索)、漁協の案内 |
| 湖・ダム湖(内水面) | 釣り可能時間、ボートの航行時間、湖岸の立入禁止区、ライフジャケット常時着用 | ダム・湖の管理者、漁協、現地掲示 |
| 管理釣り場 | 営業時間、ナイター営業の有無、レギュレーション(ルアー限定、バーブレス限定等) | 管理釣り場の公式サイト・受付 |
確認のコツとして、前日までに管理者へ電話で可否と条件(入退場方法、照明や発電機の可否、清掃義務、駐車場所)を問い合わせ、当日は現地の掲示で最終確認を行う二段構えが有効です。航路や港内付近では強いライトの照射は船舶の運航を妨げる恐れがあるため、赤色灯や減光を活用し、照射方向にも配慮してください。海上安全全般の基本は海上保安庁の情報も参考になります(海上保安庁)。
子どもと釣りをする際の注意点
子どもと釣りをする際は「救命胴衣(ライフジャケット)の常時着用」と「保護者が目を離さない」ことが最重要です。 波や流れ、足場の段差、足元の濡れた藻、テトラポッドの隙間など、転倒・転落のリスクは大人以上に高くなります。堤防の内側やファミリー向けの釣り公園、管理釣り場など、落水リスクと車の動線が分離された安全なフィールドを選びましょう。


| 装備 | 重要ポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 子ども用ライフジャケット | 体重・胸囲に合うサイズ、股ベルト付き、笛・反射材付き、確実に前止め | 海・川・湖を問わず常時着用。海上保安庁も着用を強く推奨(参考)。 |
| フットウェア | 滑りにくい靴(フェルト・スパイクは場に応じて)、踵が固定できるもの | サンダルやクロックスは転倒・脱落の恐れ |
| アイ・ハンドプロテクション | 偏光グラス・帽子、針外れ対策の手袋 | キャスト時は周囲1ロッド分の間隔を確保 |
| 熱中症・寒さ対策 | 水分・塩分、日焼け止め、レインウエア、防寒着 | 季節・風雨に応じて速乾インナーを重ねる |
| 安全・衛生セット | 簡易救急セット、絆創膏、消毒、タオル、使い捨て手袋 | 釣り針の返しはバーブレス推奨 |
行動面では、キャストとランディングは必ず大人が主導し、針やトレブルフックの管理を徹底してください。防波堤の外海側・テトラ帯・磯は避け、フェンスや手すりのある釣り場を選択します。内水面では遊漁券が必要な場所が多く、採捕できる魚種・サイズ・匹数が定められているため、出発前に漁協や管理者で必ず確認しましょう(各都道府県の規則はe-Gov法令検索で確認可能)。
また、釣り糸・仕掛け・針カバーは必ず持ち帰り、ゴミの飛散防止に努めます。生き物の扱いは丁寧に行い、フグ類など有毒魚は持ち帰らず触らない、外来種の移動・放流は禁止され得ることを教えるなど、自然保護の視点もセットで学べると安全で有意義です。
釣り保険は必要か
対人・対物のトラブルに備えるため、第三者への賠償をカバーする「個人賠償責任保険」は実質的に必須と言える重要度です。 キャスト時の針が他人に当たった、自転車・車・船舶や施設を傷つけた、といった賠償リスクは海・川・湖・管理釣り場のいずれでも起こり得ます。加えて、自身のケガに備える傷害保険、タックル盗難・破損を対象とする携行品補償などを、釣行スタイルに応じて検討しましょう。
| 保険タイプ | 主な補償 | 想定シーン | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 個人賠償責任保険(個人/家族) | 対人・対物賠償(示談交渉サービス付きが多い) | キャスト事故、転倒による他者のケガ、他人の道具・車両・施設破損 | 業務中や故意は対象外が一般的。自転車特約や火災保険の特約で付帯されている場合あり |
| 傷害保険(レジャー/スポーツ) | ケガの治療費・入院・通院・死亡・後遺障害 | 堤防からの転落、釣り針刺傷、磯場での滑落 | 通院日数・対象外スポーツの有無など支払条件を確認 |
| 携行品損害(動産総合/特約) | 釣り具の盗難・破損(上限・免責あり) | ロッド破損、タックル盗難 | 紛失・置き忘れは対象外のことが多い。高額品は限度額を確認 |
| 船釣り関連(乗船者傷害など) | 乗船中のケガ、救援費用など | 遊漁船での釣行 | 遊漁船側の加入状況と補償範囲を事前確認。「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく安全管理の説明も受ける(法令はe-Gov法令検索で確認可) |
加入のポイントは、賠償の支払限度額(1億円以上が一般的)、示談交渉サービスの有無、家族全員が対象になるか、対象外となる行為(危険行為・業務利用)を事前に把握することです。クレジットカードや自転車保険、火災保険・自動車保険の特約で既に付帯しているケースもあるため、重複加入の有無を確認してから不足分を補うと効率的です。船釣りの場合は、予約時に事業者へ安全装備(ライフジャケット・非常用通信手段)と保険の説明の有無もあわせて確認しておきましょう。
まとめ
釣りは「漁業法」や都道府県の調整規則、「外来生物法」や「自然公園法」の規制に従うことが前提。水産庁・環境省・海上保安庁の情報と現地掲示を最優先に確認し、遊漁券、禁漁期間・サイズ、立入禁止を遵守。
これが資源保護と安全、地域とのトラブル防止につながるため、疑問は漁協や管理者へ必ず相談する。ライフジャケットの着用やごみの持ち帰り、撒き餌後の清掃など基本マナーも徹底。遊漁船は適正化法に基づく表示と船長の指示に従い、安全装備を確認する。

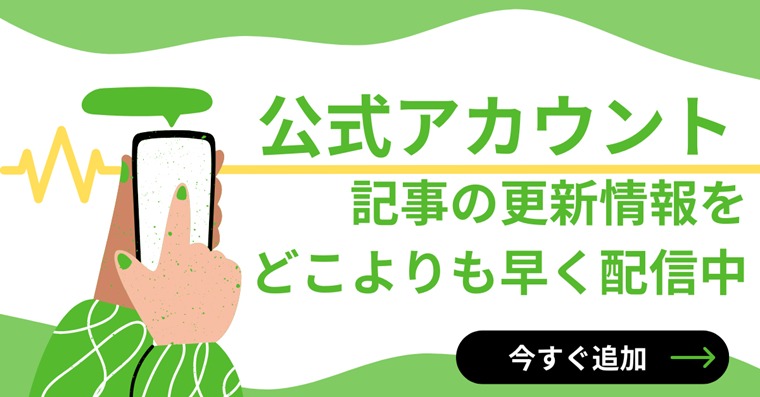

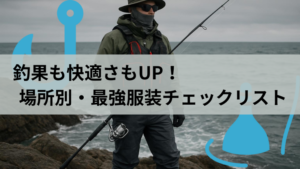
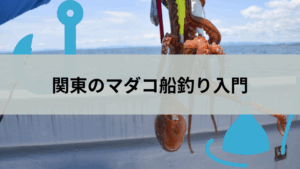

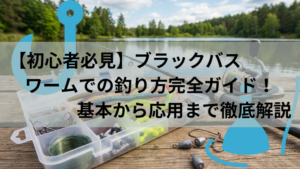
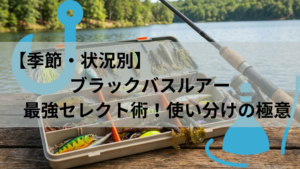
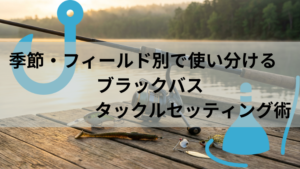
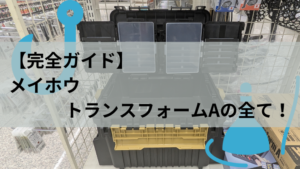
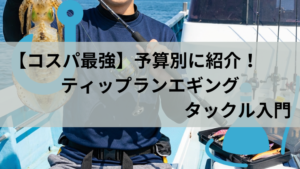
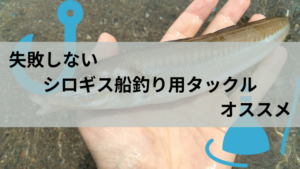
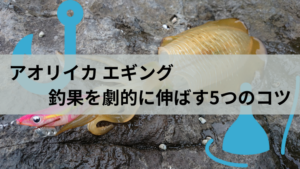
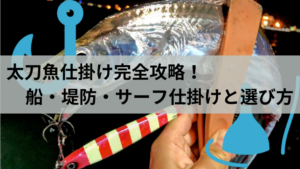
コメント